うちに長くおかかりの患者さんで下痢が続いている人がいました。ミヤBM錠を使っており1回1錠から2錠に増量したりしましたがなかなか改善しません。採血をした結果、血清アルブミン値が基準よりずいぶん低かったようです。この患者さんは蛋白漏出性胃腸症でした。この症例の患者さんに出会ったのは初めてでした。読者の方でも出会ったことが無い人も多いかもしれません。今回の記事で蛋白漏出性胃腸症について紹介します。治療法も様々なので是非学んでいって下さい。
・蛋白漏出性胃腸症のメカニズムと症状
蛋白漏出性胃腸症(Protein-losing gastroenteropathy: 以下PLE)とは血液中に存在する血漿タンパク質(特にアルブミン)が胃腸粘膜から胃腸管腔内に異常に漏出してしまい、低タンパク血症とそれに伴う症状を起こす疾患です。
低タンパク血症により血管内の浸透圧が低下してしまうので、主な症状として浮腫が症状ます。
消化管内にタンパク質が漏出することで消化管内の浸透圧が上昇し下痢を起こしやすくなります。
漏出したタンパク質が腸内で炎症を起こすと腹痛、腹部膨満感などの症状が現れます。またタンパク質の漏出によって低栄養状態になることもあります。
PLEではタンパク質と一緒にリンパ液も漏出します。胆汁酸は腸肝循環の際に一部はリンパ液を介して肝臓に戻ります。そのためリンパ液の漏出で胆汁酸が不足し、脂肪の吸収が阻害され、脂肪便がみられることがあります.
蛋白漏出性胃腸症は疾患名ではなく症候群です。この血漿タンパクが漏出してしまうのは様々な要因によって引き起こされます。主な要因と、その原因となる疾患には以下のようなものがあります。
ここまででPLEについて分かったでしょうか?続いてPLEに対する治療について見てみましょう。
PLEの治療はまずは原因疾患の治療が基本となります。それと並行して食事療法、薬物療法、外科療法を行うことになります。それぞれについて簡単に紹介します。
・食事療法
リンパ系の異常が原因の場合には高タンパク、低脂肪食を摂取します。脂肪が拡張したリンパ管から漏出して炎症を起こすためですね。場合によっては栄養剤を使用します。
成分栄養剤のエレンタール®配合内用液はアミノ酸とデキストリンで構成され、脂肪をほとんど含まないので有効です。
長鎖脂肪酸は小腸で吸収後、静脈およびリンパ管を介して、脂肪組織や筋肉、肝臓に運ばれますが、中鎖脂肪酸は炭素の数が8~12程度と小さいため、消化管から吸収後、門脈を経由して直接肝臓に運ばれます。このように中鎖脂肪酸はリンパ液を介さず吸収され、エネルギーとして分解されるため中鎖脂肪酸もPLEには使いやすいです。
中鎖脂肪酸を多く含有している栄養剤はツインライン®NF配合経腸液があります。その他にもラコール®NF配合経腸用液は含まれている脂肪の一部は中鎖脂肪酸です。
・薬物治療
浮腫を改善するために利尿剤が用いられます。低アルブミン血症の改善には人血清アルブミンなどのアルブミン製剤が用いられます。
胃腸粘膜の炎症によりタンパク質の漏出が生じている場合はプレドニゾロンやブテソニドなどのステロイドを用います。膠原病、ウィップル病、リンパ管拡張症などが原因でPLEになっている場合には有効とされています。
メネトリエ病が原因となっている場合はH2ブロッカーやPPIなどの薬物療法が行われます。
※メネトリエ病とは胃の粘膜が異常に肥厚しする疾患です。肥厚した粘膜からタンパク質が漏出し、蛋白漏出性胃腸症になることがあります。メネトリエ病では胃酸分泌を抑制し、胃粘膜を保護する必要があります。そのためH2ブロッカーやPPIなどが用いられるわけですね。
・外科療法
タンパク質の漏出の原因となっている病変が限局している場合は外科療法がされます。病変のある腸管粘膜やリンパ管を切除します。リンパ管拡張症、メネトリエ病、悪性腫瘍などが原因でPLEになっている場合に有効とされています。
今回の記事でPLEの病態と治療についてある程度理解できたでしょうか?
原因不明の下痢が続く患者さんは結構いらっしゃいます。もともとの体質だったり、過敏性腸症候群のケースが多いですが、今回のようにPLEであったり、あるいは過去に紹介した顕微鏡的大腸炎であることもあります。
※過去記事 ⇒ その下痢は薬が原因かも 顕微鏡的大腸炎について
現在服用中の薬や患者さんの採血の結果を見て薬剤師が疑いを抱くケースもあります。そのような時は医師の情報提供してあげるといいかもしれません。
にほんブログ村
記事が良かったと思ったらランキングの応援をお願いします。

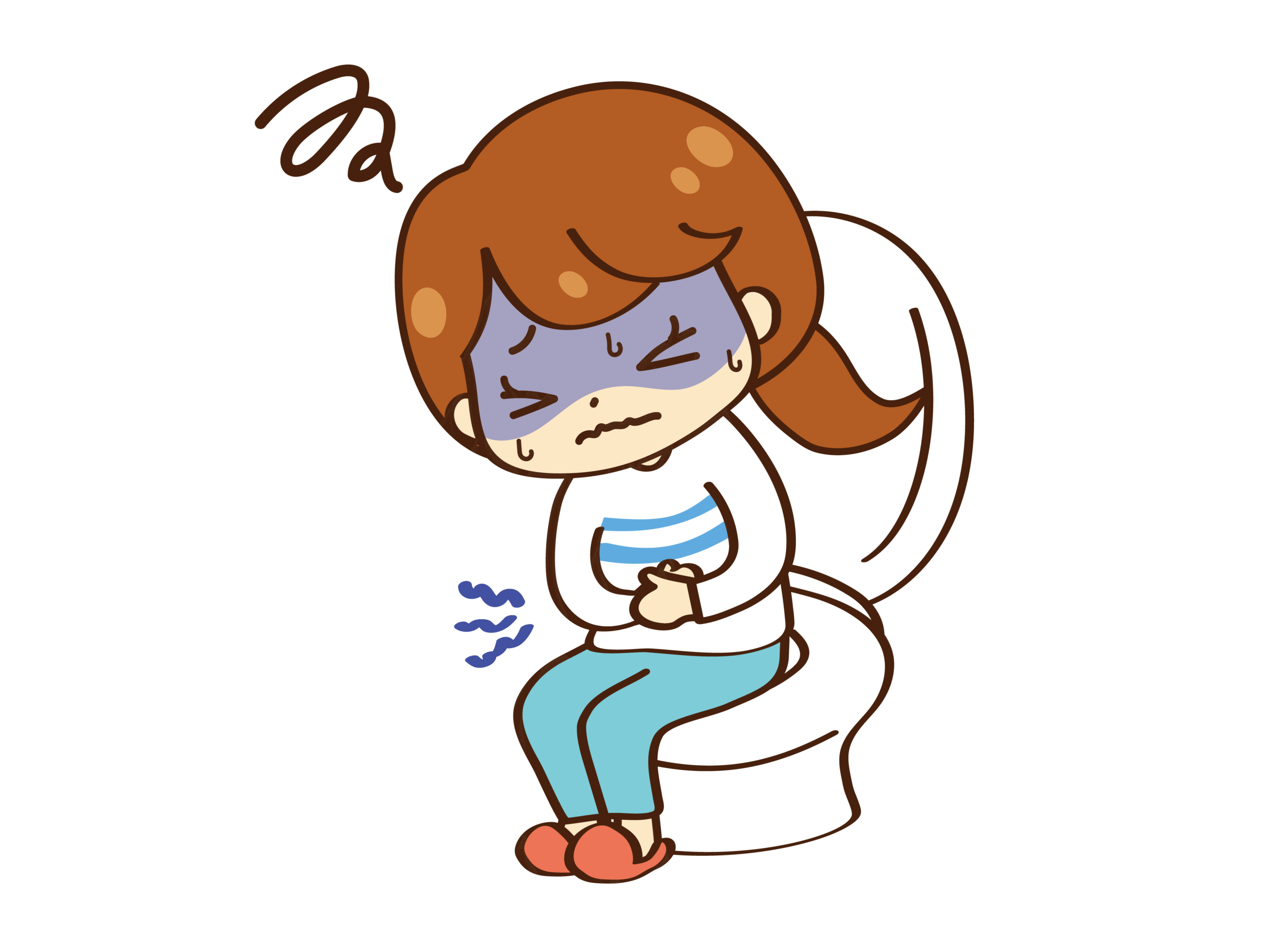

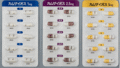
コメント